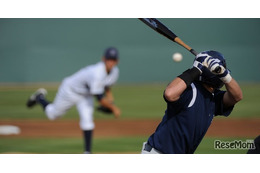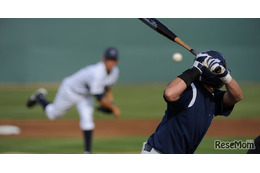その中でも近年は「考える力」や「伝える力」の比重が高まっている。求められているのは、単なる記憶力や指示とおりに動くことではない。重視されるのは、「今、この場で考える力」そして「自分の言葉で考えを伝える力」である。正解・不正解という基準ではなく、自分なりの視点やアイデアを持ち、それを相手に伝えられることが重要なのだ。
指示通りに動くロボットのような子供たちも
私立小学校では入学後に、子供同士が意見を出し合って議論したり、自分の考えを発表したりする場面が増えている。そのため、知識のインプットに偏った学びだけでは対応できないケースが目立つようになったことが背景にある。ところが、そうした時代の変化に逆行するように、小学校受験準備の現場では、本番で出題されるであろう問題を子供たちに徹底的に演習させ、まるで指示通りに動くロボットのように、セリフまで細かく教え込まれてしまうこともある。
将来なりたい職業を親が決めて子供に言わせる。さらには、ゲームで「勝ったときには3回ジャンプして喜ぶ」といった喜び方まで仕込まれている子もいる。もちろん、子供を成長させる観点ではまったく滑稽なやり方だが、親たちは合格させるために必死すぎて気付けないのだ。
難関校の試験で今、問われているのか
幼いながら徹底的に試験対策をしてきている子供に対し、自分で考え、伝える力があるか、を見るためには、訓練をしてきた子供たちのメッキをはがす必要がある。最近の入試では、学校側が子供の素の姿を見るために、あの手この手の工夫をしている。この傾向は、早稲田、慶應をはじめとする難関校の絵画課題にも表れている。
最新の慶應義塾幼稚舎の入試では、「絵本の続きを想像して絵にする」「与えられたぬいぐるみと、どこで何をしたいかを考えて描く」といった課題が出題された。これらの課題は、あらかじめ用意した答えやパターンを再現することが難しいという点で、対策しにくい内容だ。
早稲田実業学校初等部では、「楽しいことの絵を描きましょう」という身近なテーマが出題されたが、場所の指定や、絵の中に必ず使う形を指定されるなど、その場で考える即興力が試される課題となっている。
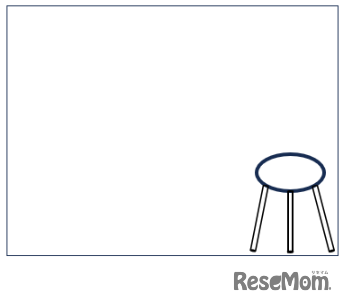
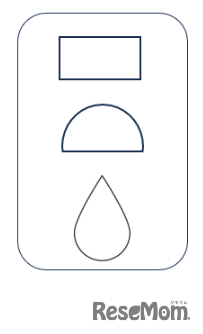 これからの小学校受験で重要になるのは…
これからの小学校受験で重要になるのは… また人気男子校の暁星小学校の行動観察では、「お話をせずに黙って背の順に並ぶ」という課題が出された。話さずに並ぶなら、ジェスチャーをしたり表情で伝えたりすれば良い。幼児でも難しいことではないのだが、行動観察では「たくさん話しなさい」と指導する幼児教室が多い中で、「話す」ことを封じられて、動揺した子も多かったようだ。
これからの小学校受験では、その場で何が求められているのかを瞬時に見極め、課題を乗り越えるためにどのような手段があるのかを考え、他者にどのように働きかけていくかといった力が問われる。受け身の知識ではなく、即興的な思考力と表現力が、今後ますます重視されていくだろう。
【執筆者】株式会社コノユメ 代表取締役 大原 英子
東京大学卒業後、大手通信会社に勤務。その後、自身の母親が30年以上にわたり主宰する受験絵画教室のメソッドをもとに、2011年に小学校受験専門の幼児教室を設立。
2022年には、教育の新しいかたちを提案すべく株式会社コノユメを設立。同年、オンラインと対面のハイブリッド型幼児教室「コノユメSCHOOL」を開校し、幼児教育業界で他社に先駆けてオンライン教材を導入。日本全国さらに海外在住の家庭からも高い支持を集め、多くの家庭に選ばれ続けている。
これまでに、慶應義塾幼稚舎・慶應義塾横浜初等部・早稲田実業学校初等部・雙葉小学校・白百合学園小学校・聖心女子学院初等科、暁星小学校、東京農業大学稲花小学校など、難関名門校への合格者を多数輩出。