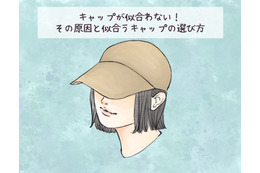首都圏では中学受験熱がヒートアップする昨今、最難関とされる男女御三家合格となれば、そのご家庭は「教育熱心なエリート一家」というイメージを持つ方も多いのではないでしょうか。
しかし、最難関K中学に合格した長男を持つ、美容クリニックで医療事務のパートをしている美子さん(仮名・44歳)は、「我が家は全然そんなタイプではないんです。気がつくと、中学受験をせざるを得ない状況になっていました」と当時を振り返ります。
今では、長男Mくん(仮名・年齢非公表)が優秀であることを素直に喜んでいるそうですが、幼少期は「他の子との違い」に悩み、「予想外の子育てに戸惑うこともありました」と話してくれました。
薬剤師の夫と医療事務の妻。下の子が生まれてはじめて気づいた「上の子への違和感」とは
美子さんは、美容クリニックに時短勤務する44歳で、医療事務の資格を持っています。現在は中学生の長男・Mくんと、小学生の双子の次男・Kくん、Yくんを育てる三兄弟の母で、薬剤師の夫・薬夫さん(仮名・46歳)、猫1匹と共に、千葉県の一戸建て住宅で暮らしています。
「子どもが男の子3人で、しかも下の子が双子となると、お察しの通り毎日が嵐のような賑やかさです。夫とは20代の頃、花火大会で知り合いました。共通の友人が花火がよく見える席を抽選で当てたので声をかけてくれて。当時、私は大学病院で受付事務をしていて、夫はMRでした」。
二人とも千葉出身で年齢も2つ違いと適度に近く、千葉から東京へ通勤していたことから話が合ったそう。出会って1カ月後にはつきあい始め、交際3年ほどで結婚しました。まもなくMくんが誕生し、6年後には不妊治療の末に双子の男の子にも恵まれます。
「双子育児は大変だと聞いていましたし、もちろん体力的にきついこともありましたが、双子のKとYを育ててみて初めて『普通の子供』というものを知ったというか、『あれ? 二人いるにしては楽かもしれない。もしかして、夜は長男一人だけの時より楽なのでは?』とさえ思ってしまったんです」
双子のKくん、Yくんは、乳児期も放っておくと朝まで寝てしまうので、わざわざ起こして授乳をしていたくらい夜泣きが少ないタイプ。そこで改めて、長男のMくんは「やっぱり普通じゃなかったんだ」と気づかされたと言います。Mくんの育児の困難はまず「寝ない」ことから始まりました。
「根っからのショートスリーパーで、赤ちゃんの頃から3歳になるまでは夜泣きがひどく、本当に大変でした。私は出産して退院した後に重度の貧血で救急搬送されて再入院し、輸血も受けることになったため、本当の新生児期は両親と夫にMを預けていました。でも、すぐに両親が疲弊してしまい、再入院からの退院後は産後ケア施設に親子入院して助産師さんにお願いしたんです」
産後ケア施設を出る頃には生後1ヵ月がたっていましたが、Mくんは1時間半から2時間おきくらいに目を覚ましてはよく泣いていたと言います。
「あの頃は夫婦揃っていつも寝不足で、ヘトヘトでした。さらに、Mは1歳になる前にはもう歩き出していたので、ベビーベッドを使わないと心配。ですからあまり添い寝もできませんでした。ベビーカーや抱っこを嫌がってすぐに泣き出し、自分で歩きたがったりするので、外出時も本当に困りました」
「うちの子って、どこか変なのかな?」とは感じるが、具体的に「どう変なのか」は言い表しにくい
そんな幼少期のMさんは、「まるいもの」がとりわけ好きだったそうです。
「例えば、赤ちゃんの頃は、おもちゃの車輪や丸い積み木を、ずーっとクルクル回していろんな角度から眺めては、床に置いてまた転がしてみたり。珍しいことではないのかもしれませんが、『同じ動作を繰り返す』時間がとても長かったのです。歩き始める頃には、私の実家のでんでん太鼓を延々と鳴らし続けていました。弟たちは、同じくらいの月齢ではでんでん太鼓は前後に振るだけでしたが、長男は何度かクルクル回して観察した後、すぐに大人みたいに手首をひねって鳴らす方法を覚えてしまいました」。
家中のまるいものがひっくり返され、鳴らされ、観察される毎日だったといいます。
「とにかくモノを回すのが好きで、ままごと用にペットボトル容器を回して外し、また回して締める、という作業を飽きもせず繰り返していました。私の睡眠時間は相変わらず短いままで、3歳くらいになると、逆に『目は覚ましているのに泣かない』ことが増えてきたのですが……。夜中にふと目を覚ますと姿が見えず、リビングへ行ったら積み木を回していたこともありました」。
とはいえ、3歳のMくんは言いつけをよく理解する方で、決して聞き分けのない子ではなかったので、「夜中に起きても一人でリビングへ行ってはいけないよ」と言い聞かせると、黙ってそれを守ったそうです。
「それでも今度は、お布団の中で遊ぶようになってしまって。動く気配で目を覚ますと、タオルケットの糸を引き抜いて丁寧に丸め、枕の上に無数の小さな玉を規則正しく一列に並べていたりしたのです。それも、朝方の4時頃のことです。小さい頃は両利きで器用だったので、丸い玉は全部同じ大きさでした。いっそ『ママも起きて』と声をかけてくれる方がまだ安心できるのに、と思うほどで、『うちの子はどこか普通と違うのだろうか』と、一人悩んでしまいました」。
「一人でアリの行列を観察している」。発達障害の検査も考えるものの、検診では指摘もされず
二人目の子どもを希望するもなかなか恵まれず、妊活費用を稼ぐために派遣で働き始めた美子さん。Mくんを保育園に預けましたが、美子さんの心配をよそに、園で問題行動を指摘されることはなかったそうです。
「3歳から6歳くらいの頃は、レゴや積み木、パズルが好きで、数にも興味を持ち始めたのですが……。パズルに至っては、絵のある表面はすぐに飽きてしまい、裏返して絵柄のない灰色の面を組み立てていました。あとは、少し協調性がないのも気になっていて、年の近い従兄弟が兄弟で遊びに来て鬼ごっこをしても、1人でアリの行列を観察していたりもしました」。
夫の薬夫さんに「もしかしたら発達障害があるのかもしれない」と相談すると、「小児科の先生に聞いてみてもいいけれど、保育園では特に問題行動を指摘されているわけでもないし、おそらく経過観察と言われるだけだと思うよ」という返事でした。
「実際、市の検診で何か問題を指摘されたことはありませんでしたし、特に病院へ行くこともしませんでした。ただ長男は、外ではしぶしぶ集団行動をするものの、母親である私には甘えがあるのか、なかなか言うことを聞かず、自分のペースで同じことを繰り返したり、何かに過集中していると『お出かけするよ』と呼びかけても声が届かなかったりすることもありました。それから、5歳、6歳と成長するにつれて文字と数字、そして恐竜に興味を持ち始め、地獄の『なぜなに期』が始まったのです」。
いくらなんでもこんなに聞くのは普通ではない。地獄すぎる「なぜ?なに?」は「詰問」の域で
知育教材や本に次々と夢中になっていったというMくんですが、少しでも分からないことがあると、納得するまで「なんで?」「どうして?」「でも、それって、おかしくない?」と質問を繰り返し、家事をしている美子さんに「問題を出して」とせがむ日々が続いたそうです。
「3歳から6歳くらいの時期を、心理学では『質問期』と呼ぶそうですが、なにせ短時間睡眠の子で、早朝の5時頃から『パパかママ、起きて。分からないことがある』と叩き起こされ、夫が『夜に起こすのはよしなさい』と叱ると一旦は落ち着くのですが、何かに夢中になるとまた忘れて聞きに来る、という繰り返しでした。私はそれを一種の『夜泣き』のようなものだと捉え、根気よく『後でね。今は寝かせて』と繰り返し言い聞かせながら添い寝をしていましたが、夫は仕事に支障が出るため、隣の部屋で寝るようになってしまいました」。
小学校に入ると、「夜中や早朝に両親を起こすのはやめようね」と納得してくれたようですが、美子さんは長く睡眠不足の日々が続いたと振り返ります。
「保育園の頃、壁にお絵かきができるようにとウォールステッカーを貼ったのですが……。ある日、お風呂から上がると、画用紙に真っ赤なクレヨンで、『精神』と書かれていて、『ヒッ』と息をのんだこともありました。しかも定規を使って書いたらしく、その直線的な筆跡がまた、何とも言えない気持ちにさせました。どうやら長男は、『精神の病気 予防と対策』という雑誌の表紙が気に入ったらしく、意味も分からず『形がかっこいいから』と真似して書いたようでした。意味も読み方も分かっていないながら、模写という意味ではちゃんと書けていたんです。ちなみに、『の病気 予防と対策』という文字は『かっこよくないから描かなかった』そうです」。
小学生になったMくんは、徐々に神童ぶりを発揮しはじめますが……。
>>>「最難関3校全勝」中受塾特待生はどのような子どもだった?「私には理解できませんが、彼にとって中受は遊びの延長、頭を使うパズルの感覚だったみたいで」
※本作は取材に基づいたストーリーですが、プライバシーの観点から、個人が特定されないよう随時事実内容に脚色を加えています。