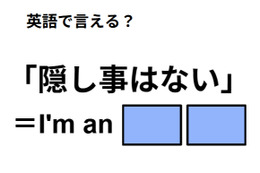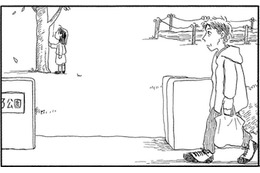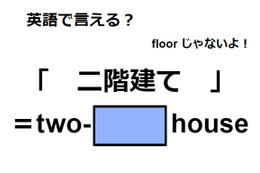長年に渡って女性特有のトラブルに向き合ってきた小川先生に、更年期時期の女性へのメッセージをいただきます。今回は「更年期の終わり方」について。
前編記事『更年期の「終わりかた」を知りたいです。閉経するとどんなことが起きていきますか?閉経前後の大まかな変化は?【専門医に聞く更年期】』に続く後編です。【女性の身体、思春期から更年期までby小川真里子先生】
月経の「終わり方」も人それぞれですが、波は落ち着いていくことが多い
更年期の終わり方にも個人差があります。いちばん多いなと感じるのは、だんだん症状が落ち着いていき、悩みを気にする時間が短くなっていくパターンでしょうか。たとえばほてりを感じる回数がだんだん減り、夜中に目が覚める回数も減りと、少しずつ落ち着いていく方が多い印象です。
いっぽうで、症状の消失具合は人によりけりです。関節症状は更年期すぎても残りやすいですし、気分の落ち込みや不安などメンタルの症状はホルモンだけでなく環境因子の影響も強く受けて強くなったり弱くなったりするようです。たとえば子どもの受験、仕事の異動や昇進、介護など、ストレス増加や新しい仕事を覚えるのが大変、そんなことで症状が強まることもよくあります。逆に受験シーズンが終わったとたんにラクになるという例もたくさんあります。
まだ更年期の最中であっても、「先生、なんだかすっきりしました!」とおっしゃる方もいます。「すっきりしたのですが、HRTは止めないとならないのでしょうか……?」とおそるおそる聞かれますが、現在のところいつやめなければならないということはないのが医学会の意見です。調子がよければ続けていいのです。が、薬ですからリスクもあります。
HRTによる乳がんリスクはもともと高くはないのですが、ほんのちょっとだけ上がる可能性があります。また、血栓症リスクもないわけではなく、HRTが体にいいことだけというわけでもありません。これらリスクと、生活の快適さや骨粗鬆症対策などQOL全体を考えたうえで、続けたいなと思ったら続けるという判断でいいと思います。
そろそろ閉経する人は、このあとどのような「トラブル」が起きていくのでしょう?
長くご受診中の患者さんの経過を見ると、55歳以降で更年期症状が落ち着くこともあれば、引き続き調子が悪いこともあります。更年期の時期を過ぎてから新しい悩み事が出現して症状に影響が出たり、メンタルの落ち込みが60代に差し掛かってもそのまま続くケースもあります。
更年期以降の女性に起こりやすい腟や外陰部、尿路の不調をGSM(閉経関連尿路性器症候群)と呼びます。女性ホルモン、エストロゲンの低下によって起きる症状の総称です。このうちのひとつとして、皮膚や粘膜の乾燥が進み、腟まわりに違和感が出やすくなるのも50歳ごろからです。
また、更年期症状ではないのですが、60代に差し掛かるころから子宮脱・膀胱脱など臓器が下がって腟から出てくる症状も増えます。このような臓器脱は、誰もそういう病気があると教えてくれないため人知れず抱え込んで悩みがちです。トイレやお風呂で膣回りを触った時に何かが指に触れたり、圧迫で排尿しづらくなったり、膣壁が下着にこすれて出血したりを、不安なままずっと我慢している方が結構いらっしゃるのです。
GSMのひとつ、尿漏れは産後に経験した人も多いと思いますが、閉経前後から顕著に問題が出てきます。関節の痛みもやはりエストロゲン低下で現れ、へバーデン結節ができたり、関節が太くなってしまったりします。
関節の痛みは閉経から少しして出てくる人が多く、まず整形外科を受診して関節リウマチとの弁別が必要ですが、関節リウマチではない場合は「女性ホルモンのせいです」と言われておしまいになりがちです。
閉経後さほど時間が経っていない場合はHRTや大豆イソフラボンサプリ、たとえばエクオールも有効ですが、時間が経ってヘバーデン結節ができてからになるとあまり対処法がないのが実情です。肘、膝などの関節痛も閉経後によく出てきます。
「更年期は太りやすくなる」、これはどう対応すればいいの?
もうひとつ、皆さんの最大の悩みが、閉経前後から太りやすくなることでしょう。太る人と痩せる人の両方います。エストロゲンがある程度低下すると男性ホルモンが優位になり、これまでの皮下脂肪型から、男性と同じようにお腹がぽっこりとする内臓脂肪型に変わります。男性も中年になると痩せていてもお腹がぽっこりしてきますが、同じようになるのです。
内臓脂肪型の肥満は、今までの感覚で数日食事を調整しても体重が戻せません。増えた分が年に1~2ずつ積み重なっていきます。いっぽう、中には痩せてく人もいるから不思議なものです。
血液の数値も悪くなっていきます。女性ホルモンが少なくなるせいでコレステロールや中性脂肪、血圧、血糖値が上がっていきます。これらは体質によるところがいちばん大きく、ご両親のどちらかが脂質異常症、高血圧だった場合はリスクが上がります。これまで健康診断の数値が優等生だった人ほど閉経後の変化には驚くでしょう。
女性の場合、脂質異常症の対策は食事と運動です。散歩するなら少し息が上がるくらいのスピードで歩くことが有効です。食事も、みなさん「私はそんな油ものも肉も食べないし」と言うのですが、実はドーナッツやデニッシュが大好きだったり、お昼にコンビニでスイーツを買っていたり、残業中におやつを食べていたりと、脂質と糖質が過多なことはよくあります。
体質の問題が大きいため、第一に食事と運動を心がけること。そして、健康診断結果に受診をと書いてあったら早めに受診してください。いやいやまだ受診するほどではないから明日から気をつければいいよね、と思う場合もあると思いますが、食事は糖尿病など厄介な成人病にも関連してくるため早めの受診がベターなのです。
糖質も、いまは極端ですよね、摂らない人はまったく摂らないし、摂る人は麺ばかり食べています。こうしたバランスも見直すきっかけがあるなら見直せるといいですよね。
もうひとつ、塩分は完全に害悪です。ですが塩分摂取量の目標を達成するのは大変なので、日々少しずつ心がけることが大事。脂質はうっかり摂っていることが多いため、やはり検査に引っかかるならば見直しが必要、そのためにも受診なのです。
自分の更年期症状がどのくらい「終わりかけているのか」を知る方法はあるか
「血液検査で更年期の終わりを調べられませんか?」と聞かれることがあります。
たとえば卵巣の機能や卵子の数を評価するAMH(抗ミュラー管ホルモン)の数値は、閉経の時点でほぼゼロになります。ですが更年期症状は閉経後も続くため、更年期症状がいつ終わるのかは検査数値では推測しにくいのです。
日本では更年期は閉経前後5年とされてはいますが、いちばん知りたい「症状が終わる時期」を知る方法はないので、症状を感じる時間が減っていくならば「終わりに向かっているんだな」と思うしかありません。なので、私の答えは「わかるといいんですけどね」、です。いずれにせよゆっくりと変化は起きていきます。
更年期症状が終わっていくことを自覚した場合、これからどうなるのか、気をつけることは何かということもよく聞かれます。
更年期の時点で気をつけないとならないのは、更年期症状を乗り切ることだけでなく、特に女性の場合はいかにこれから訪れる老後の「健康寿命」を延ばすかということです。生命的な寿命と、健康に過ごせる時期の差をなるべく縮めることがいちばん重要になるので、更年期からは骨と脂質のコントロールがとても重要になります。
というのも、女性の場合は閉経までは骨と脂質は女性ホルモンに守られていました。人生100年時代ですから、これから先の50年間は守られていない時期を生き延びないとなりません。HRTもひとつの方法にはなりますが、できることからケアしてください。
まず骨密度。計ったことない人のほうが世の中には多いので、骨検診の機会があったら骨密度も計っていただき、自分の骨密度の立ち位置を知ることが重要です。運動は更年期がスタートチャンス、10年後の60歳から何かを始めるのはかなり大変です。これからずっと続けられる趣味としての運動があるといいですね。
私の患者さんに多いのは、プールに歩きに行く人。実はプール内で歩いても骨密度は増えませんが、筋肉をつけることがとても大事です。この点で負荷が軽いフィットネスの「カーブス」に通う人が多いですね。また、ピラティスもいいでしょう。骨を強くすることと並んで筋肉を保つのも大事、何もしないとどんどん低下します。楽しんで続けられる運動を見つけておくのが大事。ゴルフもいいし、ウォーキングもいいです。
尿漏れは、必ず全員が最後は漏れるというわけではありませんが、じつは更年期ごろから人知れず尿漏れパッドを使い始める人が多いのです。尿漏れは複合因で起きていることが多く、エストロゲンの減少で起きていることも、それ以外の原因もあります。治療できるタイプもありますので、泌尿器科で相談してみてください。
いま標準体重の人も、これから太っていってしまうと糖尿病や脂質異常症を呼んでしまいます。太ると動けなくなりがちなので、標準体重を保ってください。
かといって痩せすぎにも注意です。痩せている人のほうが骨密度が低めで骨折リスクが高い傾向があります。若いころからずっと痩せていた人は50歳を機に骨密度を計っていただくのをおすすめします。あまり知られていないのですが、自治体の助成があるかどうか調べて、ぜひ活用してくださいね。
70代に入るとフレイル、ロコモなども問題になってきますので、あとは体力をゆるやかに維持することが重要になります。ぜひ意識的に運動を始めてほしいと思います。
>>>更年期の「終わりかた」を知りたいです。閉経するとどんなことが起きていきますか?閉経前後の大まかな変化は?【専門医に聞く更年期】
お話/小川真里子先生
福島県立医科大学 ふくしま子ども・女性医療支援センター 医学部産科婦人科学講座 特任教授
1995年福島県立医科大学医学部卒業。慶應義塾大学病院での研修を経て、医学博士取得。2007年より東京歯科大学市川総合病院産婦人科勤務、2015年より同准教授。2022年より福島県立医科大学 特任教授。日本女性医学学会ヘルスケア専門医、指導医、幹事。日本女性心身医学会 認定医師・幹事長・評議員。日本心身医学会 心身医療専門医・代議員。2024年4月から福島県立医科大学 ふくしま子ども・女性医療支援センター 特任教授。東京・JR五反田駅のアヴァンセレディースクリニックで、毎週金曜午前に完全予約制の更年期・PMS外来もお持ちです。