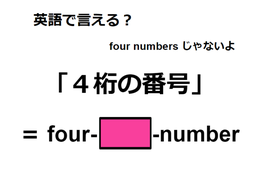夫婦問題・モラハラカウンセラーの麻野祐香です。今回は、家庭内で起きた暴力がどれほど深く家族の心を壊していくのか、そしてその影響が子どもにどのような形であらわれるのかをお伝えしたいと思います。
Fさんのご家庭は、夫45歳、妻41歳、そして中学1年生の息子さんの3人家族。夫は几帳面で、外では穏やかに見られるタイプですが、家庭の中では感情の起伏が激しく、些細なことで怒鳴ることがありました。
Fさんは、家庭内暴力と子どもの不登校という二重の悩みを抱えながら、日々を過ごしていました。
暴力のはじまりは「言葉」だった
結婚当初、夫は真面目で頼れる人でした。ところが仕事のストレスが増えるにつれ、家の中で怒りをぶつけるようになっていきました。
最初は「なんでこんな簡単なこともできないんだ」といった小さな暴言。やがて物を投げつけたり、壁を叩いたりするようになり、Fさんは常に夫の機嫌をうかがいながら暮らすようになりました。
ある晩のこと。夕食の味噌汁をひと口飲んだ夫が、顔をしかめて箸を置きました。
「なんだこれ、味うっすいな」
Fさんが「いつもと同じだけど」と言いかけた瞬間、夫はテーブルを拳で叩きつけました。
「なんだこんなもん食えるか!」
その怒鳴り声に、息子がびくっと肩をすくめました。Fさんはとっさに立ち上がり、震える声で「ごめんなさい、すぐ作り直すから……」と謝りながら、味噌汁の茶碗を取り上げて再び台所へ向かいました。その場の空気を壊さないために、謝るしかなかったのです。
夫はその日を境に、いつでも怒鳴るようになりました。「子どもの前では怒鳴るのをやめて」と訴えても、夫は「お前が俺を怒らせるからだ」と逆に責め立てます。どんな理由であっても、謝るのはいつもFさんの役目でした。
暴言や暴力の根底には、「自分の言葉や態度で相手を支配することで優位に立つ」という心理があります。相手を抑え込むことでしか、夫自身が安心できないのです。
夫の行動と心理には、いくつかの特徴が見られます。
■怒鳴る・叩くなどの爆発行動
→ 相手を沈黙させることで、瞬間的に“支配できた”と感じ、安心する。
■責任転嫁
→ 「お前が悪い」と言うことで、罪悪感や無力感を避けようとする。
■支配の確認
→ 家族が怯えたり、謝ったりする様子を見ることで、「自分は上だ」と感じる。
■慢性的な不安の裏返し
→ 心の奥には「自分はダメな人間だ」という強い恐れがあり、それを隠すために声を荒げて相手を抑えようとする。
Fさんがどれほど気を遣っても、夫の不安は決して満たされません。だからこそ、怒りと暴力は“止まらない儀式”のように日々繰り返されていくのです。
家庭内暴力が不登校を引き起こすメカニズム
息子が学校へ行けなくなったのは、夫の怒鳴り声が日常になってしまった頃でした。
夜になると悪夢でうなされ、「音が怖い」「寝たくない」と言って、Fさんの布団に潜り込むようになりました。 朝になると「学校に行きたくない」と言い出し、体を起こそうとすると頭痛や腹痛を訴えるのです。
Fさんは「甘やかさないほうがいいのか、休ませたほうがいいのか」判断がつかず、ただ寄り添うしかありませんでした。
病院に連れて行っても、異常は見つかりませんでした。 医師は「ストレスかもしれませんね」と言いましたが、そのストレスの原因が夫の怒鳴り声だとは、言えませんでした。
このケースのように家庭内に暴力、暴言や怒鳴り声がある場合、子どもは常に「次に何が起きるか分からない」と言う緊張状態で過ごしています。この慢性的な緊張は、脳にとって“危険信号が鳴り続けている”のと同じです。そのため、体は常に戦闘モードに入り、心と身体が休まらなくなります。
寝ても疲れが取れず、頭痛や腹痛が続き、学校に行く準備をするだけで息苦しさを感じることもあります。「怠けている」のではなく、 心と身体が“限界を超えて動けない状態”なのです。さらに、家庭の中で暴力を目にすると、子どもは「世界は危険な場所だ」という前提を持つようになります。
安心して人と関わる力が育たず、友人関係にも不安を感じやすくなります。その結果、学校という集団生活の場が怖くなってしまうのです。
家庭は本来、心を休める場所のはずです。けれど、そこで恐怖を感じ続けると、子どもにとって「家」も「学校」も、どちらも安全な場所ではなくなります。息子さんが布団から出られなくなったのは、怠けでも反抗でもなく、生き延びるための心の防衛反応でした。
家庭の中で起こる怒鳴り声は、子どもの心に深い傷を刻みます。 怖いという感情すら感じなくなるほど、内側が麻痺してしまう。 感情を“凍らせる”ことで自分を守ろうとするのです。
Fさんは息子の気持ちを理解しつつ、「この子をどうしたら救えるのか」答えが見えませんでした。
家庭内に暴言や罵声がある限り、どんなに母親が頑張っても、子どもの心は安心を取り戻せません。「安心できない家庭」では、子どもの心と体に次のような変化が起こります。
子どもの心に起きていること
■常に警戒状態になる(過覚醒)
→ 「いつ怒鳴り声が聞こえるか」と神経を張りつめ、リラックスできない。
■感情が麻痺する(凍りつき反応)
→ 怖さを感じないように心がシャットダウンし、笑えなくなる。
■身体化症状が出る
→ 頭痛・腹痛・倦怠感など、心の痛みが身体の不調として現れる。
■自己否定の芽が育つ
→ 「自分が悪いからパパが怒る」と思い込み、自己肯定感が急激に下がる。
家庭が安全な場所でなくなったとき、子どもは「自分の居場所はない」と感じます。それが、不登校やひきこもりの始まりでした。
本編では、夫の暴言がどのように母と子の心を壊していったのかをお伝えしました。
▶▶「『おまえのせいで家がめちゃくちゃだ』責任転嫁する夫。暴力の連鎖を止める“母の決断”とは」
では、限界まで追い詰められた母子が、どうやって“支配の輪”から抜け出したのかをお届けします。