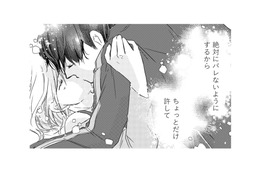高齢の親をもつ多くの方からよく聞かれるのが、「もしものとき、親に何をしておいてもらえばいいのか分からない」という声。病気やケガは、ある日突然やってきます。認知症もいつ始まるかは誰にもわかりません。そこで“まだ元気なうちにやっておいてもらいたい”ことをンキング形式でまとめてみました。前回の相続セミナーでも大人気だった1級ファイナンシャルプランニング技能士の土方朋(ひじかた・とも)さんにお話をおうかがいしました。
PROFILE
土方朋(ひじかたとも)/1級ファイナンシャルプランニング技能士
2008年三井住友銀行入行
2021年三井住友銀行退職
2022年準備期間を経て、AMI FINANCIAL DESIGNを設立
【第5位】「親の希望」を聞かせてほしい
―意外に多い声が、「自分の希望を教えてくれたら、もっとサポートしやすいのに」というものでした。
「そうなんです。子供としてもやっぱり、親の希望に寄り添いたいんですよね。『介護が必要になったときは、施設がいいのか、家で暮らしたいのか』『延命治療についてどう考えているのか』など、子どもとしては“親の本音”を知りたいと思っています。でも、親のほうも『迷惑をかけたくない』という気持ちが先に立って、なかなか本音を話してくれないことが多いんです」
―たしかに、「子どもに迷惑をかけたくない」ってよく聞きますね。
「でも実は、何も伝えずに突然”判断ができない状態”になる方が、結果的に子どもにとって負担が大きいんです。だからこそ、元気なうちに『私はこうしたい』という気持ちを、少しずつでも共有してほしい。これが“子どもにとっての安心”になるんです。”親が元気なうちに、やっておいてほしいこと”それは、資産や不動産の整理だけではありません。“どんな最期を迎えたいか”“どこで暮らしたいか”という、“生き方”に関する話もできるいいですね。相続の話を通して親子で、『何を残すか』と同時に、『どう生きたいか』を話すのもとても大切です」

【第4位】遺言書は「書き方」によって意味が変わると知ってほしい
―遺言を作るとき、例えば、配偶者と子供2人が相続人の場合、会社を引き継ぐ長男に全て渡したい場合は「全部、長男に相続させる」と書けばいいのでしょうか?
「実は、それが大きな落とし穴なんです。遺言書の内容次第では、ほかの相続人から『遺留分侵害』としてお金を請求される可能性があります。
『遺留分』とは、法定相続人が最低限もらえると法律で定められている取り分のこと。たとえば、配偶者や子どもは、本来もらえる法定相続分の半分を保障されており、それを無視するような遺言内容(例:「すべてを長男に相続させる」)があると、「侵害額請求」という法的な争いに発展することがあります。
つまり、『遺言があれば大丈夫』というわけではなく、もめない遺言の書き方が重要です。バランスや家族への想いをきちんと伝える内容にしたり、可能であれば専門家のチェックを受けることもおすすめです。
実際、『遺言はあったのに、兄弟で争いになってしまった』というケースも少なくありません。正しい形式と配慮のある中身で、“もめない”遺言書を残しておくことが、家族への最大の思いやりになります」

【第3位】認知症になる前に、「資産管理」の体制を決めておいてほしい
―「認知症になる前にやってほしいこと」この声も、最近は非常に多くなってきています。
「そうですね、認知症になってしまうと、自分で財産の管理や売却ができなくなります。そうなる前に、信頼できる家族に任せる仕組みを作っておく『家族信託』という制度があるのですが、現実はあまり知られていないんですよね。
家族信託は、”お金や不動産の管理を、家族に託す”という制度で、認知症になる前に契約しておくことが必要です。
認知症になると、あらゆる手続きが“できなくなってしまうので有効な手段ですね。例えば、実家の売却や銀行の預金の引き出しも難しくなる場合がありますので、そんな”もしも”に備える方法の一つです。
遺言と違って、“生前の資産管理”も可能です。例えば、親が認知症になっても、子どもが代わりに実家を売却して施設費用に充てることができます。家族信託のやり方は司法書士や弁護士などと契約内容を決める必要がありますが、“家族の希望に沿った”仕組みを柔軟に設計できるのが強みです。亡くなった後の遺言と家族信託による生きている間の資産管理のセットで対策できるのがポイントです」
【第2位】「誰に、何を渡すか」明確にしておいてほしい
―相続についても、「揉めたくないからこそ、事前に決めておいてほしい」という声が多いようです。
「そうですね。特に不動産を複数持っている場合、どの不動産を誰に渡すのかを明確にしておくことが大切です。土地や建物は現金と違って、分けるのが難しいので、『もめた原因が不動産だった』というケースはとても多いです。子供の側から早いうちから『〇〇がほしい』というのは遠慮してしまいますし、また親の側から話し出したとしても、話しているうちに『私はまだ生きている!』と争い出してしまうケースも少なくありません。そういうときは、遺言書ではなく家族への手紙やエンディングノートから始めてもいいと思います。誰がどの家に住むのか、先祖代々の土地をどう守りたいのか、など、想いを書いてもらうところから始めてみるのもいいですね」

【第1位】どこに何があるか、書いておいてほしい
―圧倒的に多い声が、「どこに何があるかがわからないと困る」というものだそうですね。
「そうなんです。お金のことも大事ですが、それ以前に、
・保険証券がどこにあるか
・どの銀行と取引があるのか
・持ち家の名義は誰か
といった基本的な情報がわからないという声がとても多いですね。実際に、親が倒れて入院したとき、保険の申請をしたくても『書類がどこかわからない』っていう話はとても多いです。親が突然、認知症や突然の病気・ケガがあると、それまでそのうち聞こう、と思っていたことが一気に聞けなくなります。だからこそ、元気なうちに『どの金融機関と取引があるか』『何にいくら支払っているか』といった、基本の“情報の棚卸し”を一緒にしておくことをおすすめしています」
親が元気な今こそ、「話しておく」が最大の親孝行
いざというとき、困るのはいつも“何も決まっていなかった”ということ。
親が倒れてからでは遅いのです。
「まだ元気だからいいやではなく、元気な今だからこそ、話せる・決められるということを伝えてあげてほしいです。親は『そんな話をすると子どもに嫌がられるかな…』と遠慮している方も多いんです」
子ども世代が「これからのために、一緒に準備しよう」という姿勢を見せることで、親も安心して想いを語れるようになります。
「うちの親、まだ元気だけど…」、「私はまだ大丈夫」という状態の今こそが始めどきです!
土方先生と直接お話できる無料イベントを開催します!
相続の基本と生前贈与について、土方先生が詳しく解説してくれます。相続はやろうと思ってもなかなか進まないもの。そんなモヤモヤも解決して、一つずつ進んでいくことができます。特に生前贈与は2024年に法改正があり知らないと後悔することも。今年中に生前贈与を考えている方はこのタイミングの参加がおすすめ。ぜひ土方さんに直接会って相談してみたいと思った方のためにスペシャル企画を開催いたします。
「今から備えたい相続の基本と失敗しない生前贈与のコツ」

開催日程:2025年10月31日(金)13:00〜14:30(開場:12:30)
開催場所:主婦の友社(東京都品川区上大崎3-1-1目黒セントラルスクエア内)定員50名 ※最低催行人数5名
講師:1級ファイナンシャルプランニング技能士 土方朋さん
参加費:無料
★【無料】セミナー応募フォームはこちら★
※お申し込み多数の場合は抽選となる場合がございます。
※お申し込み後、事務局より3営業日以内にご連絡差し上げます。
「相続は、思いやりのリレー」と語る土方朋さんが直接相続の基礎を教えてくれるセミナーです。主婦の友社とニッポン放送「生活の窓口」の共催で行います。相続という人生の大きな課題に、少しでも多くの方に参加いただきたいという思いで、出版社とラジオ局がともに連携して企画いたしました。ぜひ、この機会をお見逃しなく!
<セミナー参加後は土方さんによる個別相談会も実施>
開催日程:2025年11月5日(水)、11月7日(金)、11月12日(水)
10:00 11:30 13:30 15:00
開催場所:ニッポン放送(東京都有楽町) 生活の窓口
※個別相談は事前予約制ですので10月30日実施の本セミナー終了後にご案内いたします。
▼土方さんの他のお話を読む▼
>>お金のプロが語る「相続でもめる家族の傾向は…」【もめない相続】のための5つのステップも
https://youyoutime.jp/articles/10011860
>>「相続のこと後回しにしていませんか」家族間で“もやもや”しないために専門家が最も重視するコト
https://youyoutime.jp/articles/10011864
取材・文/橋本夏子