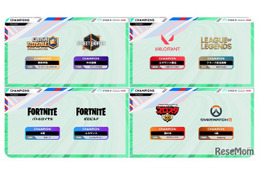小学校受験は「親の試験」でもある
願書や面接で学校側が見ているのは、ともに子供を育てていく「共育パートナー」としての家庭の適性である。学校の教育理念やプログラムを正しく理解していなかったが故に入学後のトラブルも増えている。私立小学校は教育理念が明確である。その教育について正しく理解し、方向性を共有できるかが問われている。願書や面接の対策を徹底している家庭も増え、学校側は子供同様「家庭の素の姿」をあぶりだすことに苦慮している。願書は熟慮し推敲して提出することができるが、面接は一発勝負。その場で表情を含めて素の姿が出やすい場であるため、学校側も面接でのようすを重視している。
面接で「親子の関係性」はどこで見られるのか
近年の小学校受験の面接では、志望理由や教育方針、子供の長所・短所といった定番の質問に加え、「親子の関係性」を見極めるような問いが増えてきている。家庭という最小の教育環境の質が問われていると言って良い。たとえば、雙葉小学校では「幼稚園や保育園の行事を通してお子さまが成長したことを、お子さまにお話ください」という質問が父母両方に対して出された。これは一見すると日常的なエピソードを求めるような問いだが、実は非常に多くの要素を含んでいる。
まず、行事に対しての親の関わり方が見られている。どれだけわが子を見守ってきたか、どんな瞬間に成長を感じたか。その視点が明確であればあるほど、親子が日常的に心を通わせていることが伝わる。次に、「参加してよかった」「上手にできた」といった表面的な成果ではなく、わが子がどう努力し、何を感じ取り、どんな変化を見せたのかといった過程への目配りが求められている。
さらに両親それぞれに同じ質問が投げかけられているということは、多角的視点で成長をひも解ける家庭か、ということもわかるのだ。
そして極めつけは、「その話を子供に向かって話す」という構成にある。これは面接官が親子の関係性をその場で見極めるための設問でもある。普段から会話をしている親子であれば、自然に視線が合い、子供はうれしそうに反応を示す。しかし、向き合う時間が少ない家庭では、子供が驚いた表情を見せたり、視線をそらしてしまったりする。言葉の内容以上に、目線や表情といった非言語の要素が、親子の日常を如実に映し出すのである。
このような設問にしっかりと向き合うには、普段から「わが子をどのように見ているか」「一緒にどんな時間を過ごしてきたか」を振り返ることが不可欠だ。塾や講習で練習するだけでは通用しない。関係性は一朝一夕には築けないからこそ、日々の生活が見えるのだ。
模範解答は通用しない
また、学習院初等科では、「宿題をやりたがらないとき、どう声をかけますか?」という質問があった。入学後の生活を想定した現実的なシチュエーションであり、学校側が実際に気にかけていることでもある。入学後、親がどのように子供と関わり、学びを支えていくのか。その家庭の対応力が見られているといえる。
こうした問いに対し、「どのように答えるべきか」と模範解答を求める親の声も多く聞かれる。重要なのは正解を探すことではない。学校側が知りたいのは、その家庭なりの姿勢や価値観、子供への向き合い方である。
子供が宿題をやりたがらないというのは、どの家庭でも起こり得ることだ。学校側もそれを十分に理解している。完璧な対応や理想的な解決策を求めているのではない。そうした困難な場面をリアルに想定して、親がどのように声をかけ、どう寄り添っていくか。一緒に悩み、考え、伴走していく姿勢こそが評価の対象となっている。だからこそ、取り繕った表面的な解答ではなく、家庭の価値観に根ざした等身大の答えが、面接の場では何よりも説得力をもつのだ。
直前期を「気合いで乗り切る」は危険
小学校受験の直前期を「最後の追い込み」とアクセル全開にしてしまう家庭が多い。しかし、この時期に過度なプレッシャーをかけることは、かえって逆効果となる。元気がなくなったり、ケアレスミスが増えるだけでなく、体や表情にストレスが出てしまう子供もいる。
「ここまで来たら気合いで乗り越えるしかない」と精神論に走る家庭ほど、やるべきことが見えなくなっている傾向がある。小学校受験では、まだ手書きの願書提出といったアナログな対応が求められる学校も多い。その際に、簡易書留・速達などの郵送方法、必着指定、消印有効など、細かな指定があり、かなり気を使うポイントだ。願書はいつ・どこに・どう出すのかだけでなく、兄弟がいる場合は面接や考査日の送迎はどうするか、など具体的な事柄を事前に書き出し、1つずつ整理しておく必要がある。
このようなタスクが一気に増える直前期は、ただでさえ時間に追われている親の精神的・身体的負担が極限となる。その中で、子供の学習量をさらに増やし、プレッシャーをかけるとどうなるか。親子の心身の疲弊の一途となることは想像にたやすい。
直前期の落とし穴…「頑張りすぎ」が親子を追い詰める
毎年、追い込みによる歪みがいくつもの家庭で見られる。
Aさんの家庭:親子ともに明るい笑顔で、ひときわ元気な挨拶が目を引く家庭だっだ。しかし、夏休みの講習では、子供の声が小さくなり、9月の講習では母親の化粧っけがなくなり、顔色も悪くげっそりと痩せていた。子供も情緒が不安定になり、うまく絵が描けないと「もう僕はだめなんだ」「こんな絵はいらない」と作品を破り捨ててしまうような状態に陥っていた。
Bさんの家庭:復習を徹底して行っていた家庭。毎回「正解」を子供が記憶する形の復習を行っていたため、子供には「これを聞かれたら必ずこの答えを言うように」と強く刷り込まれていた。直前期の面接演習では、質問の意図とずれた答えをしても、本人は気づかず、親から教え込まれた模範回答をロボットのように繰り返すだけ。表情にも余裕がなく、自分の言葉で語る力がすっかり失われていた。
これらは直前期に間違えることを許さず、完璧を求めすぎた結果である。頑張りの方向を誤ると、子供本来の力どころか、親子の関係性すら揺らいでしまう。直前期に必要なのは、知識やスキルの詰め込みではなく、親子の心と体を整え、これまで積み重ねてきた力を落ち着いて出せる状態をつくることだ。
過去の合格者の家庭では「最後は子供を追い詰めないように生活することが1番大変でした」と話を聞くことも多い。親は、愛するわが子が不合格という結果にならないためにもっとやらなくては、という思いと、追い詰めてはいけないという気持ちの板挟みになるのだ。直前期の仕上げとして必要なことは、子供の知識を増やすことではなく、過去にやったことを定着させて実力に変えること。生活リズムや体調、気持ちを落ち着け、本番に向けた土台をしっかり築くことが何より大切だ。特に暑さによる体調不良が増える夏は、「詰める」より「整える」意識が重要になる。
 直前期に意識したいチェックリスト10
直前期に意識したいチェックリスト10・ 親も子も睡眠時間は足りているか
・ 朝型の生活になっているか
・ 過度な学習・通塾スケジュールになっていないか
・ 出願校を決め、出願スケジュールを整理できているか
・ 願書の準備は進んでいるか
・ 面接練習を行っているか
・ 遊びや自由時間が確保されているか
・ 子供の「できていること」に目を向け伝えているか
・ 家族での会話やふれあいの時間があるか
・ 合否よりも「成長が大事」という視点をもてているか
ペーパーの丸を1つ獲得するために、子供の心身をすり減らし、もっと大事なものを失っていないだろうか。親としては「できないことをできるようにしたい」と思いがちだ。しかし、私立小学校側は、5~6歳の幼児に正解や結果を求めているわけではない。本番では、難しくてもあきらめずに取り組む、初めてのモノ・コトに対して工夫して取り組む力、他の子との関わり、などを複合的に見られていることを忘れてはいけない。
【執筆者】株式会社コノユメ 代表取締役 大原 英子
東京大学卒業後、大手通信会社に勤務。その後、自身の母親が30年以上にわたり主宰する受験絵画教室のメソッドをもとに、2011年に小学校受験専門の幼児教室を設立。
2022年には、教育の新しいかたちを提案すべく株式会社コノユメを設立。同年、オンラインと対面のハイブリッド型幼児教室「コノユメSCHOOL」を開校し、幼児教育業界で他社に先駆けてオンライン教材を導入。日本全国さらに海外在住の家庭からも高い支持を集め、多くの家庭に選ばれ続けている。
これまでに、慶應義塾幼稚舎・慶應義塾横浜初等部・早稲田実業学校初等部・雙葉小学校・白百合学園小学校・聖心女子学院初等科、暁星小学校、東京農業大学稲花小学校など、難関名門校への合格者を多数輩出。