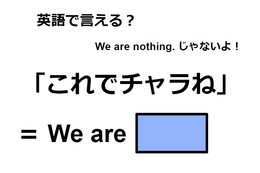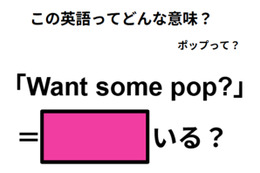モラハラ・夫婦問題カウンセラーの麻野祐香です。
「長年、夫のモラハラに耐え続けてきたのに…。私に向けられたのは、味方であるはずの子どもからの冷たい言葉でした」
気づけば、子どもがモラハラ夫の言動をなぞるようになり、母親を軽んじ、見下すようになっていた…。今回は、そんなEさんのお話をご紹介します。
※本人が特定できないよう設定を変更してあります
※写真はイメージです
夫のコピーのようになった長女
「もう限界だと思ったんです」
Eさんはそう話してくれました。
夫の理不尽な怒鳴り声や無視、あからさまな見下しは、長年にわたって続いていました。
その態度は、気づけば娘にも移っていったのです。特に娘が中学生になった頃から、夫と同じような言葉づかいや態度を見せるようになり、Eさんは家庭内での孤立感に深く傷つき、心がすり減っていきました。
かけがえのない大切な子どもだからこそ、心を込めて育ててきたはずでした。それなのに、父親が母親に暴言を吐いたり馬鹿にする姿を見てきた娘は、同じように母親を攻撃するようになってしまったのです。
さらに、父親に気に入られようとするかのように、母親を見下す態度が目立つようになり、「パパのほうが正しい」と繰り返し言うように。そして、冷たい視線でEさんを見るようになっていったのです。
家の中では、モラハラ夫が王様のように振る舞い、長女はその「側近」のように振る舞っていました。そして次女とEさんは、静かに居場所を探す毎日を送っていました。
長女が頻繁に放つ言葉 「ママってほんと面倒くさい」「パパが言ってた通りだね」
そのどれもが、夫の言葉とそっくりでした。夫は、自分に従順で都合のいい長女には、愛情を注ぎ、プレゼントを買い与え、甘やかします。
反対に、自分に口答えをし、母親に寄り添おうとする次女には、あからさまに冷たい態度を取り、「生意気だ」「お前なんか知らない」と怒鳴ることもありました。夫にとって、自分に意見する人間は“敵”であり、娘たちもまた“自分の支配下にある存在”でなければならなかったのです。
Eさんは、どんなに長女に話しかけても、その態度が変わらないことに絶望していました。母として、愛し、守り、育ててきたはずの娘が、目の前では自分を冷笑し、傷つけてくる“加害者のような存在”に変わってしまったのです。
「こんなに愛してきたのに、どうしてなの…」
父親と同じように、無視したり、馬鹿にしたりする長女を、Eさんは自分の子どもだと理解しているはずなのに、愛しさを感じられなくなっていきました。
そんな自分の感情に気づいたとき、Eさんは母親としての自分が壊れていくのを感じていました。
「母親」ではなく「家政婦」扱いされる日常
夫や長女が家庭内でEさんを軽んじるような態度をとる一方で、Eさんは毎日の送迎、学校との連絡、塾や習い事のスケジュール管理、食事の準備、進路説明会や面談など、家庭の土台となるすべてを黙々と担ってきました。
それでも、長女の中では「パパは正しい」「ママは間違っている」というイメージがすっかり固定されていたのです。娘と夫が同じように自分を見下すようになったことで、Eさんは「まるで家政婦のように、都合のいい召使いとして扱われている」と感じるようになっていきました。家庭内で発言しても無視され、感謝の言葉ひとつもない日々が当たり前になっていました。
「どんな時も家族のために動かないといけない」
そんな思いが残っていました。しかし心を通わせる会話もなく、自分が「母親」ではなく「ただ利用される存在」に成り果ててしまったように感じ、生きる気力さえ奪われていくようでした。
子どもが「加害者側」につく心のメカニズム
一緒に暮らしている家庭内でモラハラが続くと、そこには明確な“ヒエラルキー(上下関係)”が生まれます。父親が母親に対して支配的な態度をとり、怒鳴る、無視する、見下すといった行動を繰り返す中で、子どもは日常的に繰り返される家庭内の力関係を見て、「強い方についたほうが自分を守れる」と感じることがあります。
母親がどんなに頑張っても、“弱い側”に見えてしまうのです。
「被害者になるくらいなら加害者側につこう」
そんな無意識の防衛反応が、心の奥で働くことがあります。
力のある側に身を寄せることで、自分を守ろうとする。この心の動きが、長女が父親についた背景にはあったのです。
これは「同一化」と呼ばれる心理現象です。特に思春期は、自我が強くなり、親を客観的に見る時期です。モラハラの父親のそばにいるほうが安心だと感じてしまうと、たとえ大好きな母親でも、その気持ちに蓋をして父親側に同調してしまうことがあるのです。
Eさんは毎日、自分の存在価値を問い直していました。
「私は、家族の中で何なのか」
長女が父親に同調するようになった一方で、次女はEさんの気持ちに寄り添い、母親としての存在を認めてくれていました。
なぜ次女は長女と同じように父親の側に行かなかったのでしょうか。 次女には、生まれ持った性格や感受性の違いがあったのかもしれません。 家庭の中で起きていることを冷静に受け止め、母親の悲しみを敏感に感じ取る子だったからこそ、父や姉の態度に染まることなく、Eさんの心に寄り添ってくれたのです。
その優しさが、孤独の中にいたEさんの心を、かろうじて支えていたのです。
「母を選ばなかった娘」
ある日の夕食のとき、Eさんが一生懸命作った食事を、夫が「こんな不味い飯、食えるか」と吐き捨てるように言いました。長女も「ママ、料理下手だよね。ダメ母(笑)」と夫に同調し、2人はそのまま外に食事に出て行ってしまったのです。
キッチンに残されたEさんは立ちすくんでいました。そんなEさんに、次女は笑顔で「ママのご飯、美味しいよ。一緒に食べよう」と言ってくれました。その一言で、Eさんは泣きたい気持ちを抑え、次女と一緒に気分を変えて食事を取ることができました。
そして、ついにEさんは決断します。夫と長女が外食に出て行ったあの夜、Eさんの中で何かがはっきりと切り替わったのです。
「このままでは、次女までもが壊れてしまう」
次女が小学校を卒業するタイミングで、Eさんは夫と別居する道を選びました。何度も長女に「一緒に来てほしい」と伝えましたが、長女は「私は、何があってもパパの側にいる」と言い、一緒に家を出ることはありませんでした。
Eさんが次女を連れて出ていく時も、長女は顔色を変えることもなく、2人を追いかけることもありませんでした。Eさんは、心を引き裂かれる思いで、次女と2人で家を出ました。その後も、長女に連絡をし、何度も説得を続けましたが、長女の決意は変わりませんでした。
本編では、モラハラ夫に影響されて変わってしまった長女との別れと、Eさんの決断についてお伝えしました。
▶▶ 「ごめんね、ママ」……モラハラ父を選んだはずの娘が、母のもとへ戻ってきた理由
では、離れて暮らした後に起きた驚きの変化と、親子が再び歩み寄るまでの物語をお届けします。