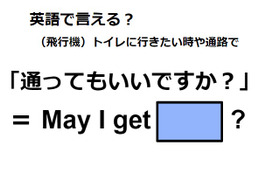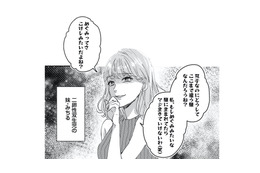こんにちは、再春館製薬所の田野岡亮太です。
私は研究開発部に属し、さまざまな商品に携わってきました。その過程で、たとえば漢方原料が土地土地で少しずつ性質を変えること、四季のうちでも変わることを知り、やがて人間の心身そのものが気候風土に大きく影響を受けていることに深い興味を持つようになりました。中医学を学び、国際薬膳調理師の資格も獲得、いまもまた新たな活動を続けています。
1年に二十四めぐる「節気」のありさまと養生について、ここ熊本からメッセージをお送りします。
【田野岡メソッド/二十四節気のかんたん養生】
コホンといったら、もう「肺」の気が上がっています
咳はどうして出るのか。西洋医学ならば喉から気管支にかけての炎症と説明されると思います。いっぽう中医学では、「肺の気が上がっている」と捉えます。肺の機能は肝の機能との連携関係があり、肺の気は降りていることが正常とイメージします。肺が少し良くない状態になると、肺の気が降りずに上がってしまい…結果、コホンとなっていると考えます。
ここで大事なのが、コホンの状態の肺は「少し良くない状態」になっているということです。肺は「潤っていると心地よい」という性質があるので、外気が少し乾燥し始めただけでも翌朝にはコホンとなったりします。秋の空気はいつ乾燥が進むかわかりにくいですよね。今の時季はまだ乾燥がそこまで進んでいないので、外気が乾燥する前の対策として、肺を潤わせておくことが大切です。
では、潤いとはどんな食材を摂ってケアすると良いのか。「秋は白い食材」がおすすめとよく言われます。例えば白きくらげ、大根、はちみつ。これらの食材は身体の中のどこでどんな働きをしてくれるか…というと、肺の経絡に入って潤いを生み出してくれる働きをします。豆腐は大腸で潤いを生み出す働きをしてくれます。肺と大腸は表裏関係なので、大腸のケアは肺にとっても嬉しいケアとなります。結果的に、これらの食材を俯瞰して見ると…みんな“白い”。秋は肺・大腸を潤してくれる白い食材がおすすめなので、「秋は白い食材」と言われます。
身体を潤すための白い食材を取り入れたいが、白ければ何でもいいわけではなくて…?

“肺の機能にうれしい食材”でおススメなのは、白きくらげ、大根、はちみつ、梨、しめじ、クコ、みずな、杏仁、鮭、ねぎなどが挙がります。
これらの“肺の機能にうれしい食材” の中で、おススメのトップバッターは白きくらげです。最近ではスーパーの乾物コーナーで目にすることが多くなって嬉しい限りです! 乾燥した状態で売られているので、重くもなく気軽に購入いただけると思います。白きくらげを使ったおススメレシピは「豆腐ハンバーグの白きくらげソーがけ」です。
作り方は、まず“豆腐ハンバーグ”を作ります。木綿豆腐(150g)に重しをのせて水分を絞り出し、玉ねぎ(1/2個)をみじん切りにします。ボウルで豚ひき肉(100g)を粘り気が出るまでよく混ぜ合せた後、木綿豆腐・玉ねぎ・薄力粉(大さじ2)を入れてこねます。その後、半分量にして楕円形にして、空気を抜きます。中火で熱したフライパンにごま油をひき、ハンバーグの表裏に焼き色がつくまで熱した後、ふたをして4分ほど蒸し焼きにします。
次に“白きくらげソース”を作ります。白きくらげは1分ほど湯通しをして、2~3cm程度の大きさにちぎります。食べやすい大きさに切ったマイタケをハンバーグを焼いたフライパンで続けて炒め、水でもどしたクコ・白きくらげ・しょうゆ(大さじ1)・みりん(大さじ2)・塩(小さじ1/2)・酒(小さじ1)を加えた後、水溶き片栗粉でとろみをつけます。
ハンバーグを器にもりつけ、上から白きくらげソースをかけて、みずなをつけ合わせたら完成です。
おススメのトップバッターの白きくらげは「身体に潤いを補って、肺の機能を助ける」働きが期待できます。また、白きくらげに合わせたクコは「潤いで肺の機能を助ける」働きが期待でき、ハンバーグを構成する豚肉は「身体に気と潤いを補う」働き、豆腐には「身体の乾燥に潤いを補う」働きが期待できます。さらに、つけ合わせのみずなは「肺の機能を助ける」働きが期待できるので、「肺の機能にとって嬉しい食材ばかり」のレシピとしておススメです。
>>>つづいて、まさかすぎる組み合わせが登場!旬のフルーツと、なんと、あの魚??