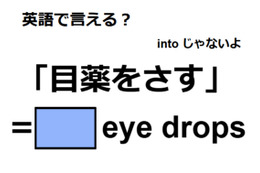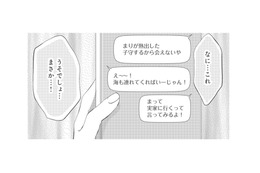1965年生まれ、1996年に渡英。イギリス東南部に位置するブライトンで低所得者が無料で子どもを預けられる託児所の保育士として働いた経験を持ち、エッセイ、ルポ、小説でもヒットを飛ばすブレィディみかこさん。2017年『子どもたちの階級闘争』、2019年『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』が各賞を受賞したことは記憶に新しいでしょう。
今年6月に新刊『SISTER “FOOT” EMPATHY シスター フット エンパシー』を上梓したみかこさんに、イギリスで女性として暮らす目線で見る日本について伺います。
日本の女性は真面目すぎるかもしれない。知らず知らずのうちに働きすぎていると思います

――そもそもイギリスのお母さんはあまりご飯を作らないですよね。
それは人にもよると思いますけど、でも一般的には、日本では朝から卵を焼いてお味噌汁も作るけれど、イギリスでイングリッシュブレックファストなんて作るのは週末くらいで、朝っぱらから火を使って調理しているママ友は少ないですね。
イギリス人は作らないけど、インド系のご家庭はお母さんが朝からしっかりお料理をしている場合もあったり、それは出自における習慣の差もあるかも。でも、日本は家事があまりにも多い気がします。イギリスのお母さんたちは早起きしてキャラ弁のような凝ったものは作らないし、ランチはサンドイッチにポテチの小さい袋、バナナ持たせて終わりです。
そういえば、友人のイギリス人男性から「聞いたよ、日本の女性は朝から魚を焼いてスープをつくるんだって? 信じがたい。毎日、毎日、なんでそんなことをするんだ!」と言われたことがありました(笑)。日本人女性はみんなそうだと思われると困るんですけど、そういうステレオタイプがあるのは事実です。
最近は趣味で料理をする男性も増えたし、外食が高いこともあり、晩ご飯は作るご家庭が多いですが、忙しく働いていたらそんなに手のこんだものは作りません。週末にはローストディナー、たとえばオーブンでローストビーフを焼いたりしますが、平日はディナーパーティーでもなければそんなに凝ったものは作っていない印象です。
――日本の女性はあんまりに家事が多すぎるから、夜ちょっと出かけてみたいな余裕が皆無、従っていく場所も生まれてこない。家事とはこなすべき義務タスクだと捉えていて、この量が多いのかどうかまで考えたことがありませんでした。
本当に切実なんじゃないでしょうか。一緒にお仕事している編集者でも、お子さんがいらっしゃる方は本当に忙しそうです。みんな家事をきっちりとやってますし、お子さんが何人かいて、しかも小さかったりすると、身を削って育児もしていて、仕事の手も抜かずにがんばった結果、自分自身が病気になっちゃったり。みんな、もっと休まないとです。
――ところが子どもが中学に進学したら、子どもが運動部のお母さんたちはみんな5時起きになりました。
5時!? うそでしょ、なんで朝5時に起きないとならないんですか?
――7時から部活の朝練なので6時過ぎに家を出る、子どもを起こして朝ごはんを食べさせてお弁当も持たせてとなると5時です。
学校に売店はないんですか? ないならパンか何か持って行かせればいいんじゃないの? 中学生でしょう、朝だって自分で起きてコーンフレーク食べることはできますよね。
――それだと糖質過剰で身体が作れない、たんぱく質を入れたお弁当を持たせてくれと顧問から指導が入るそうです。
ちょっとそれはイギリス在住者の感覚では理解できない現象です。第三者が、そこまで個人の家庭内に干渉してくるなんて。学校の先生がそんなプライバシーにまで干渉してきたら、イギリスなら保護者が反発して大騒ぎになりそうです。
日本人女性は世界でいちばん睡眠時間が短いと言われますが、朝5時起きでは、睡眠時間が確保できるわけがない。もっとしっかり寝てほしい。もっと休んでほしいです。
人は自分と違う考えの人との接触で「変わっていける」。何歳になってもまだ変わることができる

――私は80年代に英国と生活様式の近いオーストラリアに1年ホームステイしましたが、お母さんは朝起きてきませんし、家事量も少なく、当時すでに洗濯乾燥機や食洗機での自動化も進んでいました。ただ、夜に徒歩でパブに行けるのはパブがそこかしこにある英国ならではですね。サードプレイスがあるのはうらやましい話です。
もしも日本に、女性が気軽に出かけられる場所が少ないのなら、足元で何か始めてみればいいんじゃないですかね。あとは、誘われたら乗ってみる。「うーん、ちょっとどうかな……」と気乗りしないまま行った場に限って、実は思いがけない新しい体験や出会いが待っていたりしますし。
ボランティアもいいですよね、イギリスではみんな当たり前のようにボランティアを1つ2つやっていますから、そういう活動もサードプレイスになっている。
日常で顔を合わせる人が家庭と職場のメンバーだけというのは閉塞感が高まりませんか? それをもう閉塞感とすら感じないくらい、当然のように毎日毎日同じ顔触れと接しているのかもしれませんが。第三の場所を見つけて全然違う人たちと会うと、これまで当然と思って従っていた常識からも解放されて、突破口が見つかったりします。
――お話を伺いながら、いいな、私も何かしたいなとどんどん思い始めていますが、かといって行く場所が思い当たりません。
サードプレイスは、なにも物理的な場所でなくてもいい。もちろん拠点があればいちばんいいけれど、何かを一緒に行うグループでもいい。たとえば公園を掃除するような、ここに参加すると普段喋らないような人たちと必然的に喋ることになる集団です。
私は地域の元公営住宅地に住んでいて、公民館もあるので、地域の人たちとフードバンクをやっています。これは、イギリスでインフレが進んだ数年前、賞味期限が近かったり、不要になったりしたものをみんなでシェアする活動が地域で起きて、それが発展してできた場所です。
こういう活動に週日に参加できるのはリタイア後の人か大学生ぐらいなので、どうかするとリタイヤ後のおじいちゃんと若い女の子が2人シフトに入っていることがあります。
最初はもう全然話しが合わない。おじいちゃんは明らかに昔の男尊女卑で無意識にそういう態度を取るし、若い女の子ははっきりイヤって言い返して、険悪になってました。でも気が付くとけっこう仲よくなっている。
フードバンクには生理用品や紙おむつも置いてあるのですが、最近、そのおじいちゃんが「誰からも見えるところに生理用品が置いてあると、男性の自分しかいないときに女性が取りに行きにくいだろうから、ついたてがあったほうがいいね」なんて言い出して家から古いついたてを持ってきた。おじいちゃん、女性の気持ちを考え始めたというか、つまり、「他者の靴を履く」ことを始めているんです。
――みかこさんのキーワード、「他者の靴を履く」。他人の立場になって物事を捉えてみるというイギリスの慣用句ですね。
こういう小さい現実の話ってメディアは報じませんけど、世界中どこでも起きていると思います。人って、全然違う考えの人と付き合うと、決裂で終わることもあるけど、少しずつ変わることもあるんです。それは年齢を問いません。いくつになろうと人間は変わり得ると思います。
SNSには人と人との地に足がついた交流がなく、そこに書かれた言葉だけで議論するから、お前は間違ってると弾劾して排除して、どんどん閉じていってしまいがちです。でも、実際に顔を合わせて付き合っていくと人は変わる。
おじいちゃんだって、最初は移民の私のことを無視したりしてましたけど、それじゃ作業が進まないから言葉を交わすようになります。そうするとだんだん、結構いいところもあるなと互いに思ったりして、いろいろ日常の話もするようになる。これはエンパシーにも繋がっていると思います。
人はこうして、エンパシーを働かせながら、考え方や世代や習慣の違う人たちと混ざっていくことが可能で、その実践がまたエンパシーを伸ばす訓練になっていくように思います。
――表面的な状況から感情が動く同情や共鳴、シンパシーに対して、他者の内面を想像するエンパシー、これらは表裏一体だと。
違う環境に生まれ育った人でも、話し合うことによってお互いの考え方がどう違うのか、どういう環境でどう育ってそうなったのかを考えるようになる。おじいちゃんと向き合った若い女の子の側も、先々また自分とは世代や考え方が違う人と出会ったときに、相手の言動の出どころを想像するエンパシーを働かせることができます。
映画や本から得る知識や感動も大事ですが、人間は実際に生身で付き合いながら人間というものを学び、互いに時間をかけて変わっていくのです。こうした変化も込みでのエンパシーだろうと、最近は思っています。
つづき>>>日本の「保守・排外」が「危なすぎる」これだけの理由。「イギリスがこの15年で通った道をそのままたどっているのでは」
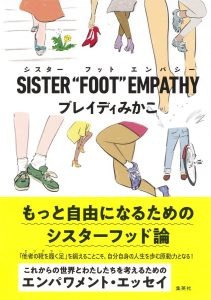
『シスターフットエンパシー』ブレイディみかこ・著 1,760円(税込)/集英社

ブレイディみかこ
撮影/黒澤俊宏