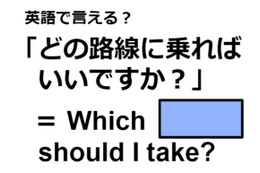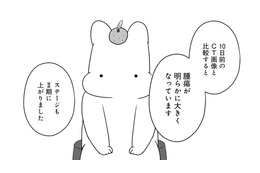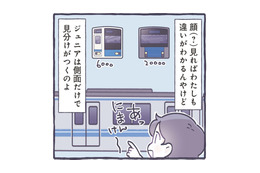こんにちは、ライターの岡本ハナです。
私の長女はADHDと強迫性障害を併せ持つ、いわゆる発達障害児ちゃん。
発達障害のある子どもを育てていると、「怒ってはいけない」と言われることがありませんか?
ただでさえ子育ては大変なのに、ハンデのある子どもが相手ならなおさらです。そう言われるたびに私は、「そんな簡単にいくわけないじゃん!」と心の中で怒りを覚えています。
何度言っても伝わらない。こちらも疲れて余裕がない。頭では冷静にしなきゃと分かっているのに、感情が先に爆発してしまうことって、きっと誰にでもあるはずです。いつも穏やかに子育てできる人がいるなら、もう仙人様として崇めたいくらい……!
今回は、つい手をあげてしまった後の後悔や、“しつけ”と“叱り方”の境界線をめぐるモヤモヤについてお話ししたいと思います。
写真はイメージです
言っても聞いてくれない…追い詰められる親のリアル
長女がADHDと強迫性障害の診断を受けたばかりの頃は、毎日が本当にしんどかったです。どう接すればいいのかもわからない。「言っても伝わらない」という状態が、一番つらかった。
イライラがどんどん積み重なって、つい手が出そうになったことも何度もあります。私は壁や物にぶつけて発散するタイプだったので、友人からは「そんなゴリラみたいなこと、やめなよ!」と止められました(苦笑)。
でも、その一言で「壁に当たるくらいなら貼ってやろう!」と謎の冷静モードになり、睡眠時間を削って一晩中壁紙を貼るという奇妙なルーティンができました(笑)。当時の家はいつの間にか、どの部屋も壁一面がレンガ調に変わっていました……。
でもね、正直に言うと、頭をパチンと叩いたこともあるし、ビンタしたこともある。レスリングみたいな取っ組み合いになったことだってあるんです。その後は、顔を合わせるのがつらくなるほど後悔しますが、冷戦を続けるわけにもいかず、何事もなかったように声をかけるしかないんですよね。
ただ、私自身の怒りがまだ完全に鎮まっていないと、「昨日のあの態度は何?」と蒸し返してしまうこともあります。その瞬間、「セカンドバトル勃発」……というスパイラルに陥るのも定番パターンです。
昭和育ちの“しつけ観”と、今のギャップ
「手をあげることは、しつけであり“大人からの愛”だ」という価値観が、かつては当たり前のように存在していました。
私は昭和生まれ。学校教育も今よりずっと厳しい時代に育ちました。先生が履いていたサンダルを脱いで生徒に向かって投げることなんて当たり前だったし、女子だけ呼び出されて肩や足を揉まされるという“謎ルール”まであったものです。
私自身も、授業中に友人とクスクス笑っただけで、床に正座させられた経験があります。今なら「過度な指導」「体罰」とされるようなことも、当時は“しつけ”の範囲内とされていました。だからこそ今、自分が育った過去の価値観と、現代の子育て観とのズレに戸惑うのかもしれません。
「怒る」と「叱る」の境界線ってどこにある?
「昭和世代だから仕方ない」なんて言い訳してみても、やっぱり手をあげてしまうのはいけないこと。後悔はすぐに押し寄せるし、私自身も深く傷ついています。
じゃあ、「叱る」とは何なのか。「怒る」とは何が違うのか。私なりの答えは、「叱る」はその子の“行動”に向き合うこと。一方で「怒る」は、親自身の“感情”に巻き込まれてしまっている状態なんじゃないかと思うのです。
もちろん、頭ではわかっています。「人格否定をしない」「落ち着いて説明する」ペアレント・トレーニングでもたくさん学んできました。
……でもね、「あれ? 今のは叱ったんじゃなくて、ただ怒鳴っただけかもしれない」と自己反省することは、正直しょっちゅうあります。
そんなことを考える時間は、だいたい寝る前。そして、どんどん深みにはまっていき、夜な夜なスマホで「怒鳴る 子ども 悪影響」と検索してしまうのです(苦笑)。
本編では、発達障害をもつ娘と向き合う中で、「怒る」と「叱る」の違いに悩み、自己嫌悪を繰り返す日々についてお届けしました。
▶▶ 「完璧じゃなくていい」発達障害の娘と一緒に生きる、私なりの子育ての着地
では、伝わらないことに悩みながらも「それでも一緒に生きていく」と決めた、私の子育てへの思いをお話しします。